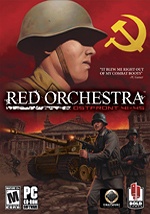|
更新: 10 / 07 / 01 公開: 06 / 05 / 06 目指すは地上戦闘シミュレーター、硬派なマルチ専用 FPS
開発: Tripwire
Interactive Red Orchestra: Ostfront 41-45 (以下 RO)は、第 2 次世界大戦での独ソ戦を再現するマルチプレイ専用 FPS です。制作は Killing Floor でも知られる Tripwire Interactive。従来のミリタリー FPS のシステムを下敷きに、歩兵&戦車戦闘のディテールに徹底してこだわった作品で、数ある“リアル系” FPS のなかでも独特の魅力を持っています。 販売価格は $9.99。ダウンロード販売(Steam)を利用すれば、今すぐにプレイできます。 どんなゲームなのかな?と思われた方は こちら の動画をご覧ください。日本語で読める Wiki も充実しています。
リリースに至る経緯数年前、ミリタリーとゲームの愛好家集団によって開発がスタートした Red Orchestra は、当初 Medal of Honor 用の Mod としてリリースされるはずでした。しかし製作過程でプラットフォームを幾度か変え、最終的には Unreal Tournament 2003 (後に 2004) の Mod となります。100% アクションを重視した Unreal Tournament で、100% リアリティ重視の Mod を製作。一見無謀な試みながら、RO の目指す方向性は一定の支持を受け、リリースと同時に熱心なファンを獲得しました。 その後も RO はバージョンを重ね、着実に内容を深めていきます。2004 年夏〜冬にかけての大型アップデートではついに戦車が登場し、その際 Red Orchestra: Combined Arms と改名しました。これにより RO に集まる注目は更に大きなものとなり、2005 年初めには、各所で 2004 年度 Mod Of The Year 賞を受賞するまでに至ります(GameSpot DLX 他)。
Computer Games Magazine 2004 Mod of the year Epic 社の主催する Make Something Unreal Contest 2004 で優勝した開発チームは、その賞品として Unreal エンジン(2.5、 3.0)の使用権を獲得しました。彼らはこれを期に Tripwire Interactive 社を設立、最初のプロジェクトとしてスタンドアローン版 RO の制作に取り掛かります。独自に改良を施した Unreal エンジン 2.5 をベースに、一から作り直した旧コンテンツに数々の新要素を加えて、RO は再び大変貌を遂げました。こうして完成したのが、この Red Orchestra: Ostfront 41-45 です。 どんなゲームかRO は、第 2 次世界大戦を背景に、歩兵や戦車が入り乱れて戦うマルチプレイ専用 FPS です。プレイヤーは各自ドイツ軍かソビエト軍に所属して戦闘に参加し、死んではリスポーンを繰り返しながら、戦友とともに作戦目標の達成を狙います。主眼となるマルチプレイヤーモードの他、BOT を使った一人用の練習モードがついています。 RO はどんなゲームですか、と聞かれてのデザイナーの答え: 「我々はただのミリタリーゲームではなく地上戦シミュレーター、例えば IL-2 (フライトシム)の地上戦闘版と呼べるゲームを作りたい。そのために徹底したリサーチを行い、当時の歩兵戦闘にかかわったあらゆる要素の正確な再現を目指している」。 このコメントが示す通り、RO の開発チームは 「プレイヤーを戦場に放り込む」 という使い古された宣伝文句を、本気で実現しようとしています。普通の FPS ならウケを狙って妥協するはずの部分でも、RO はゲーム性を破壊しないギリギリまでリアリティを優先しています。Mod をルーツとし、小さなスタジオが開発していることもあってか、けっしてゲームとして完璧ではないと思います。発売からだいぶ時間が経った今では、正直言ってところどころエンジンや技術力などの限界、古さを感じてしまう部分もあります。しかしそれでも RO は、今なお一部の方を「こんな FPS がやりたかった!」と感激させるだけの、独自性と魅力を備えたゲームではないかと思います。ミリタリー FPS にこだわりのある方は、ぜひ一度お試しください。
RO でのあなたは、平凡な兵士にすぎません。何をするにももっさりとした動作で、走ればすぐ息が切れます。ジャンプでの攻撃回避や走り回りながらの戦闘はまず不可能です。弾に当たってしまえば一発でも命取り、かすめただけでも恐怖で一瞬視力が奪われます。与えられる銃は当時実際に使われた旧式銃で、連射できればいい方、多くのプレイヤーは単発のボルトアクションライフルのみを手に戦うこととなります。どの銃も癖が強く、激しい反動や照準の揺れ、重力による弾の落下といった要素が射撃を非常に難しくしています。 遠距離の戦闘は、低火力と射撃の難しさのおかげで、互いに命中弾を与えられず長引くことがしばしばあります。至近距離では、下手に銃を撃つより銃剣で突撃した方が強かった、などということもあります。こうしたローテクでスローな独特の銃撃戦は、個々の兵士が圧倒的火力を持つ現代戦 FPS では味わえない部分でしょう。スローであるために戦闘中に考える時間があり、一発当たれば即死というゲーム的に危険なバランスでありながら、自分に落ち度のまったくない理不尽な死は、意外と(あくまで意外と)少ないゲームです。銃声やマズルフラッシュを元に敵の配置を推測、敵が見えたらすぐに身を隠し、頭を一瞬出して数と装備を確認して、対処方法を考え、銃を委託し慎重に狙いをつけて……と、マウスさばきや反応速度の勝負に終わらず、賢く戦うことを知っているプレイヤーが生き延びる戦闘システムとなっています。スピード感や爽快感はありませんが、かわりに制約を克服する楽しさと、たまらない緊張感とがあります。
武器に注がれた情熱も、特筆すべき点でしょう。銃声、スペック、特徴の再現などはもちろんのこと、それぞれ実銃を元にモデリングされ、細かなアニメーションから構えたときのスケール感まで、それらしい感じがよく出ています。ライフルのボルト操作を手動で行う、同じ銃でも距離が離れれば銃声が変わる、手榴弾が稀に不発を起こす、銃身のオーバーヒート速度が気温の影響を受ける、といった凝り様には驚かされるばかり。当時の武器に詳しい方なら、それだけでも楽しめるかもしれません。詳しくない方も、適当に撃っているだけで「手応え」のようなものが感じられるほどの、素晴らしい作りこみではないかと思います。 開発当初 RO は、歩兵のみに焦点を当てたゲームでした。しかし現在のバージョンでは戦車を初めとする車両も登場、大きな役割を果たします。戦車での戦闘は、突き詰めていけば複雑な処理が必要となるため、多くのゲームで簡略化されてしまうパートですが、ここでも RO は姿勢を貫き通しています。装甲の貫通判定で距離と入射角が考慮されたり、キャタピラの破損が再現されている FPS は、ほとんど見たことがありません。細かな部分では荒削りで、戦車シミュレーター並とまではいきませんが、FPS としては破格の緻密さと言えるはずです。 何よりの RO の魅力は、こうした凝った戦闘システムに加えて、悲壮さすら漂う精緻なマップ、そして迫力あるエフェクトやサウンドの相乗効果が生み出す「戦場の雰囲気」だと思います。ふりそそぐ砲撃の中、戦車のキャタピラ音におびえながら塹壕を這い回り、ライフルの遅いリロードに悪態をついていると、なんだかこう本当に戦場であがいているかのような気が一瞬しないでもありません。
リアリティを重視しすぎたゲームはつまらない、とよく言われます。しかし RO はその限りではないはずです。チーム戦ゲームとして楽しめるように、システムとマップ構造の両面で、じゅうぶん配慮されています。個々の兵士の戦闘能力が低い分、戦術を競い合うという意味でのゲーム性は、むしろ高いのではないかと思います。さらに最近のアップデートにより、プレイ可能人数が 32 人から 50 人前後へと大幅に増加したため、凄まじい激戦・混戦が楽しめるようになりました。現在の RO は、けっして地味だがリアルというだけではなく、時に非常に熱いミリタリー FPS となっています。 マップは、歩兵のみで戦う小サイズの歩兵マップ、戦車が加わる中サイズの混合マップ、戦車戦に重点が置かれた広大な戦車マップの 3 タイプに分かれます。製品版にはそれぞれ 4、5 個、計 15 個のマップが含まれていました。発売後のパッチで、その数はさらに大幅に増えています。見通せる距離は、最大数 km (一部の戦車マップにて)。野外での戦いをテーマとするものが多いですが、障害物や建物があちこちにあり、接近戦も頻繁に発生します。 基本ルールは、よくある陣地取りシステムで、大勢で重要な目標におしかけて、キャプチャーを狙います。マップはかなり広大ですが、両軍が攻める・守るべき場所は少数に絞られており、兵士が戦場に散らばってしまうことはありません。また、死のペナルティはさほど重くなく、倒れてもすぐ前線に復帰できます。常に両軍が対峙する明確な前線が存在し、それをどうやって押し上げ、チームを勝利に導くかが重視されるデザインです。 勝利条件を達成するために与えられる時間は短く、“キャンプ”行為だけではまず勝てません。機関銃が睨みを利かす防衛ラインをいかに突破するか、要所に押し寄せる敵をいかに撃退するか。支援砲撃を使うタイミング、戦車と歩兵の連携についても考える必要があります。どの状況にも突破口があり、その穴を衝けるかどうかはチームの結束次第です。ラウンド終了のタイムリミットまで、両軍のチームワークと戦術が幾度も試されることになります。
個人的に感じた問題点も書いておきます。すぐ思いつくのは、高いクオリティと評価にもかかわらず、知名度が低くプレイヤー人口が少ないことです。特に国内のプレイヤーは多くはありません。このページを作った理由でもあります。グラフィックは、ご覧の通りあくまでそれなりです(2010 年現在ではそれなりを通り越して時代遅れと言うべきかもしれません)。マルチプレイ専用のうえに BOT の能力が低いので、オフラインでしか遊べないという方は、まったく買う価値がないでしょう。その他、いまだに修正されない小さなバグもいくつか残っています。 また、シミュレーターと呼ぶにはおかしな部分、再現の足りない部分があるかと思います。戦車がちょっとした障害物にスタックする(踏み潰せない)、壁の貫通が再現されていない、クルーの脱出に要する時間がない(即車外に飛び出す)、装甲貫通システムの矛盾点などがよく指摘されます。一方アクションゲームとしては、戦車マップ(戦車が大量に登場する広大なマップ)の存在そのものに不満を持たれる方もおられるでしょう。確かに戦車戦は駆け引きがあって面白いのですが、時としてテンポが悪く、イライラさせられる瞬間があります。よくできた歩兵戦部分とくらべ、戦車戦部分ではもう少し改良が必要ではないかとの印象を受けます。歩兵戦部分でも、破壊力の極めて高い手榴弾がリスポーンごとに気前良く再支給されるため、参加人数が多いと前線でひっきりなしに手榴弾が爆発を始めて、いわゆるボンバーマン状態になってしまうのは残念な点です。 開発チームは、発売後もバグ修正だけにとどまらず、ゲーム性の拡充に努めていくと約束しています。実際、2006 年 3 月 14
日の発売以来、幾度もパッチがリリースされ、新マップや武器、車両など、多くのコンテンツが追加されてきました(すべて無料で!)。また SDK
をリリースするなど、Mod
へのサポートにも非常に積極的です。現在では、ファンによって制作された無数のカスタムマップはもちろんのこと、西部戦線ものなどいくつかの大型
Mod がすでにリリースされ、本家とはまた違う味わいで人気を博しています。RO の続編制作も快調のようですし、Tripwire
Interactive とコミュニティの努力によって、今後も RO は発展を続けていきそうです。 XASIS
GAME (A 5/6) デモはないのか以上、ひたすら絶賛してみましたが、私はすでに RO に大きく思い入れがあるため、公平な評価とはいえません。海外ゲームサイトのレビューでも指摘される通り、RO のプレイ感覚は一風変わっています。多少とっつきづらく、慣れるまでは爽快感よりもストレスの方が強いかもしれません。遊んでみたがまったく肌にあわない、という方もおられるはずです。 残念ながら RO には体験版がありません。購入前に RO を触ってみたいという方は、無料体験期間(Free Trial Week)中にプレイされることをおすすめいたします。この期間中は、Steam のアカウントを取るだけで、製品版とまったく同等の内容の RO を無料で遊ぶことができます。 英語、日本語化に関してRO のマニュアルやゲーム内のテキストは、すべて英語です。しかし、マルチプレイ専用のアクションゲームですから、難解な表現や長文を読む必要はまったくありません。英語が苦手という方でも、プレイ自体に問題はないかと思います。RO ランチャーとして使うことになる Steam には、日本語のメニューも用意されています。 なんと、RO のゲーム本体を日本語化してくださった方々がいらっしゃいます! 必要スペック
メモリーは 1GB 以上あった方がよさそうです。それ以下ですと、長いローディングに苦しめられることになります。その点を除けば、RO はそれほど「重い」ゲームではないでしょう。グラフィックの調整項目が豊富に用意されているので、推奨環境を完璧に満たさなくとも、問題なくプレイできるはずです。 どこで買うんですか遊ぶために必要なもの: このサイトで扱う RO は、過去 UT2004 の Mod として無料配布されたものではなく、最近製品として発売されたスタンドアローン(単体起動)版です。したがって必要なものは…
お店で買った場合、Steam で買った場合、どちらの場合でも、RO のプレイには Steam が必要となります。
お店で買う: 他のゲームと同じように、店頭で箱入りの RO を購入するわけですが、日本での販売価格はちょっと高めです。そもそも 2010 年現在ではパッケージ版の入手はかなり難しいはずですし、結局 Steam で遊ぶのは一緒なので、あえてこちらを選ぶ意味はあまりないのではないかと思います。以下は RO を販売していそうな国内通販店へのリンクです。 Steam で買う: Steam での購入にはクレジットカードが必要ですが、RO の値段は $9.99、日本円で 1000 円弱、非常にお手頃です。RO 購入を考えられている方は、こちらの方法を強く強くおすすめいたします。頻繁に $5 程度でのセールも行われています。 Steam
クライアントソフトのダウンロード(無料) Steam は Valve 社の開発した PC ゲームのオンライン流通システムです。Half-Life シリーズで大量のプレイヤーを捌いてきた Steam は、現在では比較的快適に使える信頼性の高いシステムとなっています。プレイヤーは Steam のクライアントソフトをダウンロードし、アカウントを作成します。ここまでは無料です。Steam を起動してカタログ画面からゲームを購入すると、あなたのアカウントにその旨が記録され、遊ぶのに必要なデータをダウンロードできるようになります。マニュアル類は PDF ファイルで配布されます。一連の流れは日本語で説明され、英語が読めない方でも利用できます(RO 自体は英語です)。 Steam の利点としては、認証キーではなくアカウントでプレイヤーを管理するため、ユーザー名とパスワードさえ覚えておけば、世界中どこでも、どの PC でも、購入したゲームを遊ぶことができます。またパッチのダウンロードと適用はすべて自動で行われます。 |
|
|